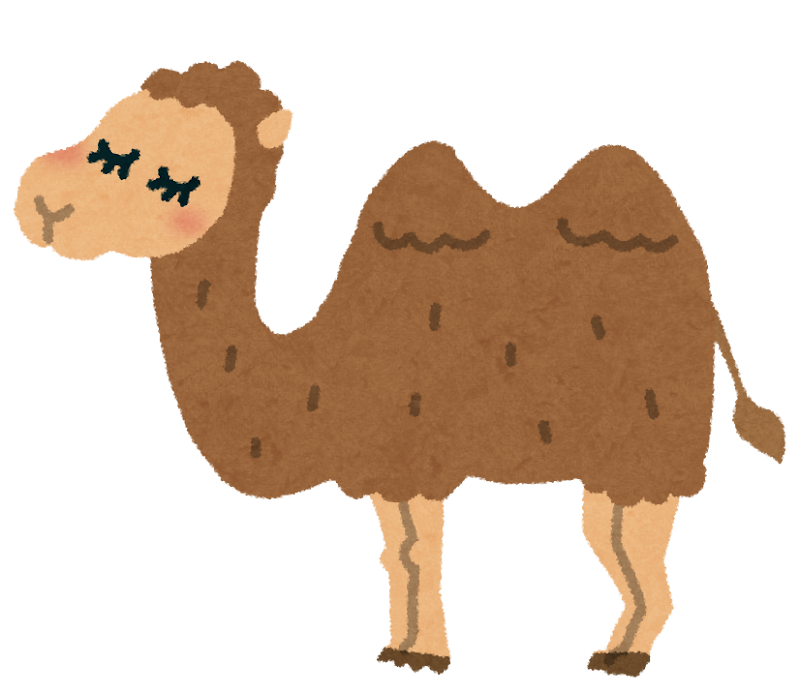比較的に暖かい日が続いている今年の12月。
服装を厚手のものにするか、このまま重ね着でいけるか、、、
日中に自転車で移動することが多く、汗ばんだりすることも。
利用者の方の家へ上がらせてもらい、
帰る際に外へ出た時は寒さが一段と身に沁みます。
皆さんはどうされているのでしょうか。
そんな12月ですが救急車が多く走っているなという印象。
少し調べたら10月下旬から多くなってきているとのことだそうです。
法人内での異動をして2年が経ち今更ですが肌に感じることができました。
ちなみに運ばれる理由は、「ヒートショク」「大掃除などによる転倒や転落、ぎっくり腰」「一酸化炭素中毒や住宅火災」「暴飲暴食による事故や病気」、年始になれば「餅がのどに詰まる」だそうです。
どれもこの時期ならではの理由ですね。
移動する方は日照時間の短さや交通状況も気を付けていただけたらと思います。
何かと忙しなくなる時期で気を付けることばかりです。
さて冒頭で話した通り、本日(12月23日)も日中は日差しが暖かくて過ごしやすいですが、どうやら年末は寒気が流れ込んで寒い年越しになると。
厚手の上着の準備をして体調管理に気を付けていきましょう。